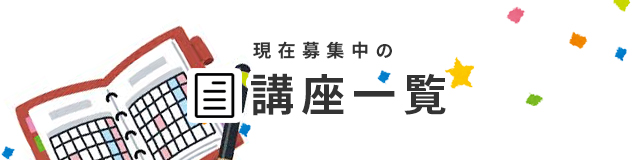コロナの1年がもうすぐ終わろうとしている。
私に限らず、この1年は「リモート」とか「オンライン」の動きが圧倒的に増えた人が多いのでは。
この流れに乗っかった人と、乗っかれなかった人とでは、行動量に大きな差が出たのではないだろうか。
前回、リモート&オンラインライフを満喫している話を書きましたが、いろいろ思うことはあるわけで…。
まず、オンラインだろうがオフラインだろうが、あんまり変わらないよなーと思う私はどうやら少数派らしい。
前回も書いたが、私はオンラインコミュニケーションを気軽にとっているのだけど、「気軽に」取れているのは、オンラインとオフラインとの違いを明確に理解し、その場に応じたコミュニケーションを取っているからだと思う。
最初こそみんな不慣れなので、接続トラブルも雑談のようなアイスブレイク的な位置づけにして笑って済ませることもできたけど、緊急事態宣言から半年も経過した今となっては、ちょっと不慣れなだけでも、慣れた人から見ればストレスに感じてしまうだろう。
つまりは、オフラインで対面で行っていたときは、まったく必要とされなかった「接続」にまつわる知識や自己解決できるスキルがいきなり求められるようになったということだ。
車を運転する人が全員事故が起きたときの対応を当たり前に求められるように、リモートワークで起きる回線やデバイス、環境設定、はては自己管理などまで全部自分で管理しなければならない。
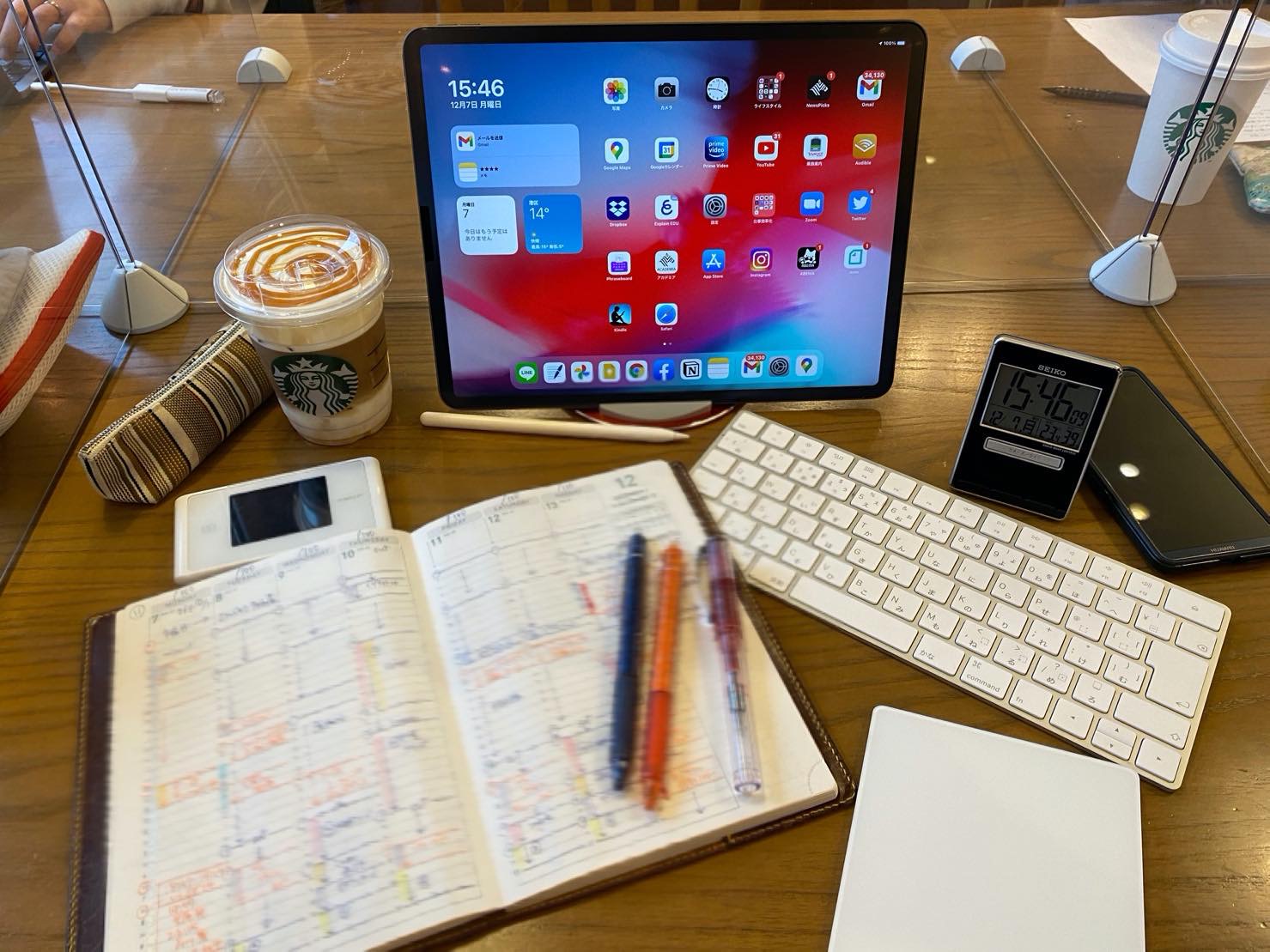
また、コミュニケーションの「テクニック」的なことも必要になってくる。
具体的には、オンラインのコミュニケーションは、受信者はリアクションを「(発信者にとって)わかりやすく」示す必要があるということだ。
コロナがきっかけで、「オンラインのコミュニケーション」と言えば、Zoomなどでオンライン会議アプリを利用しての、対面コミュニケーションを意味することが多くなった。
オンライン会議アプリを利用しての対面コミュニケーションを行うときは、相槌や表情の変化などで「聞いてます」「伝わっています」というリアクションをする必要がある。
そんな明文化されたルールなんかないけれど、自分が話す側になればよくわかる。
相手がリアルに目の前にいれば、仮に無表情で聞いていても、「聞いてます」「伝わっています」ということは伝わってくるものだ。というか、むしろ無表情はダメ出ししてくるんじゃないかと思いません?(つまり、「聞いていない」前提はありえない)
だけど、画面越しだと、表情の動きがないと、回線やデバイスに不具合があるのではないかという心配になってしまう。それまで普通に会話していたのに、2秒後には自分の声が相手に聞こえていないという状況は普通にあり得るから。
そういう、オンラインとオフラインの違いなんて誰がどう見ても明確だと思っていたのだけど、実際はそこの認識に格差がある。
そして、自分のリアクションが発信者の求めている基準に達しているかということを考えている人といない人がいて、そこにはあまりにも明確な格差がある。
そして、「テキストベース」のコミュニケーションも増えた。
こちらに関しては、コロナ前からのことなので、「受信者はリアクションを「(発信者にとって)わかりやすく」示す必要がある」というお作法についてはもはや文化として成り立っているかと思いきや、そうでもないというのが私の認識だ。
つまり、現時点では、オンラインにおけるコミュニケーションは、上級者の我慢で成り立っているということになる。
コミュニケーションという「日常生活」が、一方の我慢をベースにして成り立つというのでは長続きするわけがない。
オンラインのコミュニケーションができるようになって、いつでもどこでもつながれるようになった。
会いに行く手間が省けるぶん、頻繁に機会を持つことができるようになり、人間関係を豊かにできる選択肢を得た。
だけど、実際のところは、より豊かにしたいと思う人間関係はそう多くはないと思う。
むしろ、会うまでもないレベルの温度の人間関係に対して気軽にコミュニケーションできる機会を作ったところで、上記のようなスキルや気遣いが足りないことで結局は豊かにもならないし長続きもしない。
次回に続きます。
毎日更新しています!
★────────────────────
・パーソナルサイト
http://ohisamayoko.com
・instagram
http://instagram.com/ohisamayoko_project
・note
https://note.mu/ohisamayoko
☆────────────────────